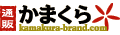ほぼ週刊サキドリニュース
2009年5月2日付の記事
新江ノ島水族館は5周年!
環境水槽リニューアル

この春、5周年を迎えた新江ノ島水族館は「環境水槽」をリニューアル。
今年度のテーマは「たいせつな命」。
5周年を記念する今回のリニューアルでは、小さな命が集まることによってさらに強く感じられる「命」の美しさにスポットをあてると共に、同じく5周年を機にスタートした「えのすいECO」を伝える展示水槽にもなっています。
<「環境水槽」展示内容概要>
○展示生物: クロホシイシモチ 250 個体
○展示意図: 小さな命が集まることによってさらに強く感じられる「命」の美しさにスポットをあてています。
○照明: 従来の水槽照明より消費電力の少ない「LEDライト」を導入。
従来の照明が1キロワットであったのに対し、150ワットとなっています。
※「環境水槽」は容量3.4トンですが、このクラスの水槽の主照明として「LED ライト」を使用した例はこれまでにはないようです。
■えのすいECO■
生物に関する生態学(エコロジー)、そして環境を考える活動や取り組み。“えのすい”はこの2つの側面から独自に「えのすいECO」を開始しました。
相模湾に隣接し湘南に位置する水族館として、今伝えられること、みなさんと一緒に楽しくできることを真剣に考え、コツコツと続けていきます。具体的には、相模湾や相模湾にくらす生物をより詳しくご紹介していくことはもちろん、一年以上にわたり毎月実施してきたビーチクリーン活動もさらに推進していきます。
また、拡大版の「えのすいECOデー」も春・秋に開催していくなど、身近なECO活動をさらに楽しく進めていきます。
今年度のテーマは「たいせつな命」。
5周年を記念する今回のリニューアルでは、小さな命が集まることによってさらに強く感じられる「命」の美しさにスポットをあてると共に、同じく5周年を機にスタートした「えのすいECO」を伝える展示水槽にもなっています。
<「環境水槽」展示内容概要>
○展示生物: クロホシイシモチ 250 個体
○展示意図: 小さな命が集まることによってさらに強く感じられる「命」の美しさにスポットをあてています。
○照明: 従来の水槽照明より消費電力の少ない「LEDライト」を導入。
従来の照明が1キロワットであったのに対し、150ワットとなっています。
※「環境水槽」は容量3.4トンですが、このクラスの水槽の主照明として「LED ライト」を使用した例はこれまでにはないようです。
■えのすいECO■
生物に関する生態学(エコロジー)、そして環境を考える活動や取り組み。“えのすい”はこの2つの側面から独自に「えのすいECO」を開始しました。
相模湾に隣接し湘南に位置する水族館として、今伝えられること、みなさんと一緒に楽しくできることを真剣に考え、コツコツと続けていきます。具体的には、相模湾や相模湾にくらす生物をより詳しくご紹介していくことはもちろん、一年以上にわたり毎月実施してきたビーチクリーン活動もさらに推進していきます。
また、拡大版の「えのすいECOデー」も春・秋に開催していくなど、身近なECO活動をさらに楽しく進めていきます。
世界初・新種の貴重な深海生物を公開
深海コーナーでは、4月26日(日)より貴重な深海生物「オウギガニ科の一種」(世界初展示)、「オオマユイガイ属の一種」(世界初展示)、「イデユウシノシタ」(新種)の生体展示を開始しました。
■世界初展示 ≪オウギガニ科の一種≫ Xanthidae gen. et. sp.
日光海山ではユノハナガニと同所的に生息しています。
ユノハナガニほど密度は高くはありませんが、ユノハナガニを採集する時に何個体か混じります。ハサミの先端が黒く、また白いユノハナガニに比べ赤褐色をした体色が特徴です。
甲幅 約2cm /2 個体展示
日光海山ではユノハナガニと同所的に生息しています。
ユノハナガニほど密度は高くはありませんが、ユノハナガニを採集する時に何個体か混じります。ハサミの先端が黒く、また白いユノハナガニに比べ赤褐色をした体色が特徴です。
甲幅 約2cm /2 個体展示

オウギガニの一種

オオマユイガイ属の一種
■世界初展示 ≪オオマユイガイ属の一種≫ Gigantidas sp.
本種は熱水噴出域付近に生息していますが、共生細菌についても詳しくはわかっていない二枚貝です。
海底の岩やハオリムシの群集に足糸と呼ばれる糸を使い付着しています。
殻長 約12cm /7 個体展示
本種は熱水噴出域付近に生息していますが、共生細菌についても詳しくはわかっていない二枚貝です。
海底の岩やハオリムシの群集に足糸と呼ばれる糸を使い付着しています。
殻長 約12cm /7 個体展示
■新 種 ≪イデユウシノシタ≫ Symphursus thermophilus
本種は2008 年に新種として記載されました。当館では
記載される前、同海域で採集された本種をアズマガレイ属の
一種として展示を行っていました。
熱水噴出域周辺やハオリムシの群集、礫の上などで見られ
海底にエサを置くと集まってきます。
体長 約8cm/5 個体展示
本種は2008 年に新種として記載されました。当館では
記載される前、同海域で採集された本種をアズマガレイ属の
一種として展示を行っていました。
熱水噴出域周辺やハオリムシの群集、礫の上などで見られ
海底にエサを置くと集まってきます。
体長 約8cm/5 個体展示

イデユウシノシタ
展示飼育を開始する「オウギガニ科の一種」「オオマユイガイ属の一種」「イデユウシノシタ」は、2009年4月10日~4月20日に行われた海洋研究開発機構(JAMSTEC)の伊豆小笠原弧明神海丘・北部マリアナ海域 日光海山調査(NT09-05)において、調査船「なつしま/ハイパードルフィン」により採集されました。
北部マリアナ海域にある日光海山には水深450~500mに熱水が噴出しており、その周辺には深海生物のユノハナガニ、オハラエビの仲間、サツマハオリムシなど非常にたくさんの生物が生息しています。
今回は日光海山の熱水噴出域、水深約460m 地点にて採集されたユノハナガニ、サツマハオリムシ、タギリカクレエビ、トウロウオハラエビの4 種に加え、世界初展示となる「オウギガニ科の一種」と「オオマユイガイ属の一種」、2008 年に新種記載された「イデユウシノシタ」の3種を展示いたしました。
新江ノ島水族館は現在、海洋研究開発機構(JAMSTEC)と深海生物の長期飼育技術の開発に関する共同研究を行っています。
北部マリアナ海域にある日光海山には水深450~500mに熱水が噴出しており、その周辺には深海生物のユノハナガニ、オハラエビの仲間、サツマハオリムシなど非常にたくさんの生物が生息しています。
今回は日光海山の熱水噴出域、水深約460m 地点にて採集されたユノハナガニ、サツマハオリムシ、タギリカクレエビ、トウロウオハラエビの4 種に加え、世界初展示となる「オウギガニ科の一種」と「オオマユイガイ属の一種」、2008 年に新種記載された「イデユウシノシタ」の3種を展示いたしました。
新江ノ島水族館は現在、海洋研究開発機構(JAMSTEC)と深海生物の長期飼育技術の開発に関する共同研究を行っています。