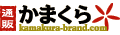鎌倉好き集まれ!shigeruさんの鎌倉リポート・第5号(2007年12月5日)
鎌倉鶴岡八幡宮の黄葉(H19-12-5)

鳥居
交通量の多い道路の前にそびえたつ大鳥居です。
鳥居を入るとすぐに朱色の橋が両側にあります。

朱色の橋

長い参道から御宮が二重に見える場所です。
鶴岡八幡宮が一望見れる場所で、両側には屋台が立っています。
鶴岡八幡宮は、康平6年(1063)源頼義公が奥州を平定して鎌倉に帰り、源氏の氏神として出陣に際してご加護を祈願した京都の石清水八幡宮を由比ヶ浜辺にお祀りしたのが始まりです。
その後、源氏再興の旗上げをした源頼朝公は、治承4年(1180)鎌倉に入るや直ちに神意を伺って由比ヶ浜辺の八幡宮を現在の地にお遷しし、 建久2年(1191)には鎌倉幕府の宗社にふさわしく上下両宮の現在の姿に整え、鎌倉の町づくりの中心としました。
その後、源氏再興の旗上げをした源頼朝公は、治承4年(1180)鎌倉に入るや直ちに神意を伺って由比ヶ浜辺の八幡宮を現在の地にお遷しし、 建久2年(1191)には鎌倉幕府の宗社にふさわしく上下両宮の現在の姿に整え、鎌倉の町づくりの中心としました。

お宮

大銀杏
県の天然記念物で、樹齢一千年余、高さ三○・五名米です。
縦長で撮った大銀杏です。

大銀杏

源平池の紅葉
この池は、春は桜、夏は蓮の花が綺麗です。