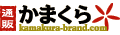鎌倉好き集まれ!春風裕さんの鎌倉リポート・第83号(2023年12月2日)
紅葉特別拝観の覚園寺と瑞泉寺を歩く
覚園寺

覚園寺山門
紅葉の時期に行われる特別拝観の覚園寺を訪れました。
数え切れないほど鎌倉を訪れている割に、覚園寺はこれが2回目です。
鎌倉駅を出たところの5番のりばから大塔宮(鎌倉宮)行きのバスに乗り、終点で降ります。
鎌倉宮の前から北北西に延びる小道を奥まで約10分ほど歩くと、覚園寺の山門が見えてきます。
数え切れないほど鎌倉を訪れている割に、覚園寺はこれが2回目です。
鎌倉駅を出たところの5番のりばから大塔宮(鎌倉宮)行きのバスに乗り、終点で降ります。
鎌倉宮の前から北北西に延びる小道を奥まで約10分ほど歩くと、覚園寺の山門が見えてきます。


覚園寺の山門を入ったところ、愛染堂前あたりの紅葉がとても綺麗でした。
覚園寺は拝観受付所から先を「祈りをささげる空間」として護持しているため、撮影・写生は禁止されています。
拝観の順路が決まっていて、まずは撮影OKの愛染堂にお参りして、拝観受付所で拝観料を納めます。
地蔵堂ややぐら、旧内海家を通り、引き返して薬師堂で説明を聴き、お参りします。
地蔵堂裏のイチョウの葉っぱが散って、黄色い絨毯のようになっていたのが印象的でした。
写真を撮れないのが、とても残念でしたが、お参りするのが本来ですから。
覚園寺は拝観受付所から先を「祈りをささげる空間」として護持しているため、撮影・写生は禁止されています。
拝観の順路が決まっていて、まずは撮影OKの愛染堂にお参りして、拝観受付所で拝観料を納めます。
地蔵堂ややぐら、旧内海家を通り、引き返して薬師堂で説明を聴き、お参りします。
地蔵堂裏のイチョウの葉っぱが散って、黄色い絨毯のようになっていたのが印象的でした。
写真を撮れないのが、とても残念でしたが、お参りするのが本来ですから。
永福寺跡
永福寺(ようふくじ)は、源頼朝が建立した寺院です。
平泉の中尊寺の二階大堂大長寿院をまねて建てたようです。宇治の平等院に似ていたと言われています。
1405年に火災にあって、室町時代の終わりに廃絶したということです。
僕が鎌倉を歩いていた最初の頃は、雑草が生えた広大な草むらだったのですが、その後整備されて今は公園のようになっています。
この日はとてもお天気が良く、陽当たりの良いこの場所は、ぽかぽかしてとても気持ちが良かったです。
平泉の中尊寺の二階大堂大長寿院をまねて建てたようです。宇治の平等院に似ていたと言われています。
1405年に火災にあって、室町時代の終わりに廃絶したということです。
僕が鎌倉を歩いていた最初の頃は、雑草が生えた広大な草むらだったのですが、その後整備されて今は公園のようになっています。
この日はとてもお天気が良く、陽当たりの良いこの場所は、ぽかぽかしてとても気持ちが良かったです。

瑞泉寺

参道

山門

本堂

どこも苦地蔵

夢窓国師の庭園

紅葉
もう紅葉しているだろうと瑞泉寺を訪れてみました。
残念ながら紅葉はあまり進んでいないようで、写真のとおり3分くらいでしょうか。
今年の気候が変なので、このまま紅葉しないのではないかと思ったりします。
山門に続く石段も、そして境内も、何だかとても寂しい風情でした。
何度か訪れている瑞泉寺ですが、これほど人が居なかったことは無かった気がします。
その代わり、とても静かなひとときを過ごせて、とても静かな瑞泉寺を堪能できました。
残念ながら紅葉はあまり進んでいないようで、写真のとおり3分くらいでしょうか。
今年の気候が変なので、このまま紅葉しないのではないかと思ったりします。
山門に続く石段も、そして境内も、何だかとても寂しい風情でした。
何度か訪れている瑞泉寺ですが、これほど人が居なかったことは無かった気がします。
その代わり、とても静かなひとときを過ごせて、とても静かな瑞泉寺を堪能できました。
鎌倉宮

手水

鎌倉宮
今日の散策の終わりは、鎌倉宮でした。
覚園寺から歩いていた時は、七五三詣での方が大勢いた気がします。
帰り道に立ち寄ると、そうでも無かったので、せっかくだからとお参りしました。
手水はいつの間にか水が出るようになっていました。コロナ禍では止めていました。
少しずつ元に戻っているのだなあと思いました。
良く晴れて、日向はぽかぽかして、気持ちの良い鎌倉散策でした。
また近いうちに歩きたいと思っています。
覚園寺から歩いていた時は、七五三詣での方が大勢いた気がします。
帰り道に立ち寄ると、そうでも無かったので、せっかくだからとお参りしました。
手水はいつの間にか水が出るようになっていました。コロナ禍では止めていました。
少しずつ元に戻っているのだなあと思いました。
良く晴れて、日向はぽかぽかして、気持ちの良い鎌倉散策でした。
また近いうちに歩きたいと思っています。