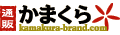鎌倉好き集まれ!いいねぇおじさんさんの鎌倉リポート・第1096号(2013年2月17日)
◇ 祈年祭 鶴岡八幡宮 (つるがおかはちまんぐう)

鶴岡八幡宮の本宮に於いて、毎年2月17日に執り行われる 「祈年祭」 に行ってみました。
真冬に戻ったような寒さに、源氏池では氷が張っていました。 旗上弁財天社裏の政子石の
傍らでは、満開の紅梅が朝陽に輝いていました。

◇ 氷が張った源氏池

◇ 旗上弁財天社の紅梅
古くは「としごいのまつり」と訓(よ)みました。 「とし」 とは 「稔り(みのり)」 の意味で、春のはじめに
あたってその年の五穀豊穣を祈るお祭がこの「祈年祭」です。
今日では商工業も含めすべての産業の発展、国家と皆様の繁栄を祈るお祭であり、毎年2月17日に
斎行されます。
古くはこの祈年祭に際し、朝廷から全国の神社に幣帛(へいはく)が頒布されていました。
今日でも、この日は皇居の宮中三殿においても祭儀が行われ天皇陛下が御親拝なされるのをはじめ
全国各地の神社で祈年祭が斎行されます。 なおこの祈年祭に対応する秋の収穫を祝うお祭が
11月の「新嘗祭」ということになりますが、農耕民族であった日本人の精神性の源に通じる「祈年祭」
と「新嘗祭」は、年に一度の「例祭」と並んで、特に重要な神事とされています。
「祭の意味」より

◇ 祓所での清めの儀式

◇ 祓所から本宮へ
社務所出た宮司、神職の皆さんは、祓所でお清めの儀式の後、境内を一列に並んで、
本宮(上宮)へ向かいます。

◇ 華やかな衣装の巫女さん
伝統的な装束に身を包んだ神職の皆さん。 4人の巫女さんは、若草色の華やかな衣装でした。
大石段を一列に並んで本宮へ上がって行きます。 大石段脇の河津桜の木が枯れてしまいま
したが、満開の桜の下だったら、一段と華やかな雰囲気に包まれたことでしょうね。

◇ 大石段を上って本宮へ

◇ 本宮から若宮へ
本宮では30分程神事が行われ、巫女さんによる「浦安の舞」が奉納されます。
楼門内へは入れず撮影も禁止です。

◇ 〃

◇ 若宮で参拝
神事を終えた一行は若宮(下宮)へ参拝した後、社務所へ戻ります。
社務所前では白梅が見頃を迎えていました。

◇ 社務所へ戻る