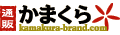鎌倉好き集まれ!十六夜さんの鎌倉リポート・第54号(2010年11月3日)
扇谷山 海蔵寺
二代鎌倉公方 足利氏満の命により

本堂
創建は応英元年(1394)開山は「心昭空外」(源翁禅師)。鎌倉公方の足利氏満の命により創建された。開基は関東管領の上杉氏定(扇谷)。本尊の薬師如来坐像の胴体部分に、もう一つの薬師の顔を納めた珍しい仏像。児護薬師(こもりやくし)と呼ばれている。鎌倉十井の一つ「底脱ノ井」がある。境内には季節の花が咲き「花の寺」として知られている。
(十一月二十三日(火曜日)まで国宝館での特別展「薬師如来と十二神将」を開催のため海蔵寺さんの薬師如来坐像は国宝館へ出張中です)
(十一月二十三日(火曜日)まで国宝館での特別展「薬師如来と十二神将」を開催のため海蔵寺さんの薬師如来坐像は国宝館へ出張中です)

三門

底脱の井
山門前の階段をおおいつくしていた萩はきれいに手入れされさっぱり、次の紅葉を待つばかりのようです。
扇ヶ谷の海蔵寺の門前にある「底脱の井」、鎌倉時代中期の武将で幕府の重臣だった安達泰盛の娘が水を汲んで桶の底が抜け、「千代能がいだく桶の底抜けて水たまらねば月もやどらじ」と詠んだ歌によるとも言われている。
扇ヶ谷の海蔵寺の門前にある「底脱の井」、鎌倉時代中期の武将で幕府の重臣だった安達泰盛の娘が水を汲んで桶の底が抜け、「千代能がいだく桶の底抜けて水たまらねば月もやどらじ」と詠んだ歌によるとも言われている。
十一月十五日 鶴岡八幡宮 七五三祈請祭


久しぶりに散策日和、八幡宮・段葛・小町通り・・・は多くの人で賑わっていました。


十一月十五日は七五三祝の日ですが、十一月三日お天気に恵まれ八幡宮境内は晴れ着の子供達で賑わいを見せていました。
江戸時代の徳川綱吉の子、徳松君がこの日に祝ったことから、十一月十五日に定着したと伝えられています。
いつの時代も子供の成長を願う親の気持ちに変わりはありません。氏神さまに詣でてご加護を頂き、日頃の感謝と共に子供の成長を祈願するのでしょう。