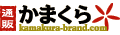鎌倉好き集まれ!JUNEさんの鎌倉リポート・第12号(2004年7月10日)
The background of the art

古陶美術館
先頃、写真教室のセンセイが、
「ここは好いよ」とあまりに強く推薦するので、
興味津々初めて訪れてみた。
美術館長のお話によると、
上物は、福井県にあった江戸時代より続く古民家を
そっくりそのまま鎌倉に移設してきたとのこと。
内装の梁や柱に使用の木材は、
廃屋となった鎌倉の民家から譲り受けたもの。
煤焼けした天井梁に残る凹凸の杭跡。
ミシミシと音を鳴らして二階へと続く階段。
黒光りした手摺りと古風な磨硝子との調和。
英国も顔負けのDIY精神が
ここにもしっかりと息づいている。
「ここは好いよ」とあまりに強く推薦するので、
興味津々初めて訪れてみた。
美術館長のお話によると、
上物は、福井県にあった江戸時代より続く古民家を
そっくりそのまま鎌倉に移設してきたとのこと。
内装の梁や柱に使用の木材は、
廃屋となった鎌倉の民家から譲り受けたもの。
煤焼けした天井梁に残る凹凸の杭跡。
ミシミシと音を鳴らして二階へと続く階段。
黒光りした手摺りと古風な磨硝子との調和。
英国も顔負けのDIY精神が
ここにもしっかりと息づいている。
常設は古瀬戸の壺や水注などの陶磁器が主であるが、
ちょうど「おひなさまと節句人形」の特別展
(~2004/7/11)が開かれていた。
立雛は、雛人形の最も古い形式で、
厄祓いの「形代」と「ひいな遊び」とが結びついたもの。
もとは紙で作られ、「流し雛」とされたもので
「紙雛」とも呼ばれている。
烏帽子に小袖・袴の男雛、小袖に細帯の女雛の素朴な姿は
室町時代の風俗をうつす。
身体の弱い我が子の健康を祈り、流し雛に願いを託す親心。
今もなお、信州松本地方で受け継がれているという。
ちょうど「おひなさまと節句人形」の特別展
(~2004/7/11)が開かれていた。
立雛は、雛人形の最も古い形式で、
厄祓いの「形代」と「ひいな遊び」とが結びついたもの。
もとは紙で作られ、「流し雛」とされたもので
「紙雛」とも呼ばれている。
烏帽子に小袖・袴の男雛、小袖に細帯の女雛の素朴な姿は
室町時代の風俗をうつす。
身体の弱い我が子の健康を祈り、流し雛に願いを託す親心。
今もなお、信州松本地方で受け継がれているという。

立雛

元禄雛
江戸時代までの節句人形は、
雛壇に向かって右側にお内裏様が鎮座していた。
昭和に入り、
日本が経済成長期の時代を突き進むなか
欧米に追いつけ追い越せの風潮を反映しつつ、
雛飾りにも欧米様式の波が押し寄せた。
これが、現在の並び(向かって左側にお内裏様)
となった所以である。
たかが雛人形と言えども、
その奥には深い歴史の重みがある。
雛壇に向かって右側にお内裏様が鎮座していた。
昭和に入り、
日本が経済成長期の時代を突き進むなか
欧米に追いつけ追い越せの風潮を反映しつつ、
雛飾りにも欧米様式の波が押し寄せた。
これが、現在の並び(向かって左側にお内裏様)
となった所以である。
たかが雛人形と言えども、
その奥には深い歴史の重みがある。
お内裏様とお雛様より一段下って
三人官女が並んでいる。
なんと、両側二人の女官は未婚者、
中央の女官は既婚者であるという。
なるほど、よく見ると
お神酒を手にした両端の女官達は振袖姿、
中央ただ1人、留袖を着た女官は、
式次第の一切を取り仕切るというしっかり者。
宮仕えにも、各人立場に准じた役割分担があった。
それにしても、
ミニチュアとはいえ 一同見事に勢揃い。
頬染めて ほろ酔い気分で 宴たけなわ。
三人官女が並んでいる。
なんと、両側二人の女官は未婚者、
中央の女官は既婚者であるという。
なるほど、よく見ると
お神酒を手にした両端の女官達は振袖姿、
中央ただ1人、留袖を着た女官は、
式次第の一切を取り仕切るというしっかり者。
宮仕えにも、各人立場に准じた役割分担があった。
それにしても、
ミニチュアとはいえ 一同見事に勢揃い。
頬染めて ほろ酔い気分で 宴たけなわ。

節句人形

源平ツリフネソウ
美術館の中庭で、偶然見つけた野の花。
サヤエンドウの花にどこか似ている趣。
決して目立たないけれど、
薄いピンクと白のコントラストが涼を誘う。
入り口軒先では、
風鈴が1つ、チリンチリンと風に揺られ
清らかな音をたてていた。
もうじき この庭にも 蝉時雨。
サヤエンドウの花にどこか似ている趣。
決して目立たないけれど、
薄いピンクと白のコントラストが涼を誘う。
入り口軒先では、
風鈴が1つ、チリンチリンと風に揺られ
清らかな音をたてていた。
もうじき この庭にも 蝉時雨。