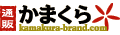鎌倉好き集まれ!JUNEさんの鎌倉リポート・第23号(2004年9月24日)
Behind the masks
去る9月18日土曜日の午後。
以前よりずっと気になっていた御霊神社の例祭を見に行く。
江ノ電の小さな踏切を渡りながら、ふとトンネルの方へ目をやる。
ひっそりと肩を寄せ合い彼岸花が咲く線路脇。
もうすぐ電車がやってくるよと囁く。
暫くして、
天高く、海からの潮風に乗って、
チャカチャカと賑やかなお囃子の音が聞こえてきた。
そ~れ、急がなきゃ。
以前よりずっと気になっていた御霊神社の例祭を見に行く。
江ノ電の小さな踏切を渡りながら、ふとトンネルの方へ目をやる。
ひっそりと肩を寄せ合い彼岸花が咲く線路脇。
もうすぐ電車がやってくるよと囁く。
暫くして、
天高く、海からの潮風に乗って、
チャカチャカと賑やかなお囃子の音が聞こえてきた。
そ~れ、急がなきゃ。

坂ノ下

例祭
俗称、権五郎神社。
もとは平安時代後期、
地元の漁師たちが祖先の霊を祀るために建立した古社である。
この日のメインは、田楽面や舞楽面をつけた十人衆が、
坂ノ下界隈を練り歩く面掛行列。
その行列に先駆けて奉納されるのが「湯立神楽」である。
赤い天狗の面をつけた宮司が槍を振りかざし舞う。
その後方、黒い天狗の面をつけたもう一人の宮司が、
いかにも悪役振りたっぷりに舞う。
隅っこのほうででオドオドと逃げ回る黒い天狗。
天を仰ぎ、勇敢にも邪悪に立ち向かう赤い天狗。
狂言にも似た両者の舞は、いつしか観客の笑いを誘う。
もとは平安時代後期、
地元の漁師たちが祖先の霊を祀るために建立した古社である。
この日のメインは、田楽面や舞楽面をつけた十人衆が、
坂ノ下界隈を練り歩く面掛行列。
その行列に先駆けて奉納されるのが「湯立神楽」である。
赤い天狗の面をつけた宮司が槍を振りかざし舞う。
その後方、黒い天狗の面をつけたもう一人の宮司が、
いかにも悪役振りたっぷりに舞う。
隅っこのほうででオドオドと逃げ回る黒い天狗。
天を仰ぎ、勇敢にも邪悪に立ち向かう赤い天狗。
狂言にも似た両者の舞は、いつしか観客の笑いを誘う。

湯立神楽
本来の湯立神楽とは、
「産土神,火の神,水の神を招神し、神々の恵みに感謝、
そして除災招福を祈る」ものであったらしい。
が、実際の湯立といえば、
神前にて大釜に沸騰した湯を囲んで行なうもので、
その湯をふりかけて身を清め(ひえぇ~っ)、
湯花や泡の立ち具合で神意を占うといった、
まさにオドロオドロしい命がけの神事。
今回、あまりの人手のため、
このおっかなびっくりシーンに遭遇できなかった。
残念…のち…安堵(ほっ)。
「産土神,火の神,水の神を招神し、神々の恵みに感謝、
そして除災招福を祈る」ものであったらしい。
が、実際の湯立といえば、
神前にて大釜に沸騰した湯を囲んで行なうもので、
その湯をふりかけて身を清め(ひえぇ~っ)、
湯花や泡の立ち具合で神意を占うといった、
まさにオドロオドロしい命がけの神事。
今回、あまりの人手のため、
このおっかなびっくりシーンに遭遇できなかった。
残念…のち…安堵(ほっ)。

面掛行列
湯立神楽に続いて、
神輿渡御の行列と共に「爺」「鬼」「鼻長」「阿亀」など
十人の面掛衆が行列する。
行列は、仏教布教を目的に上演された伎楽に由来する。
なるほど、各面は横幅が広く、男面の鼻が高いといった特徴は、
かつて歴史の教科書で見たような…?
また、行列の中心となる妊婦姿の「阿亀」は、
豊作,豊魚を「妊む」「産む」のシンボルでもあった。
観客の渦の中、お父さんの肩車に乗った幼い少年が、
行列の一人「異形」の面に驚いたのか、
いきなりわーんと泣き出した。
わかるなぁ、その気持ち。
あの面面に凝視されると、大人でもドキリとするんだよね。
神輿渡御の行列と共に「爺」「鬼」「鼻長」「阿亀」など
十人の面掛衆が行列する。
行列は、仏教布教を目的に上演された伎楽に由来する。
なるほど、各面は横幅が広く、男面の鼻が高いといった特徴は、
かつて歴史の教科書で見たような…?
また、行列の中心となる妊婦姿の「阿亀」は、
豊作,豊魚を「妊む」「産む」のシンボルでもあった。
観客の渦の中、お父さんの肩車に乗った幼い少年が、
行列の一人「異形」の面に驚いたのか、
いきなりわーんと泣き出した。
わかるなぁ、その気持ち。
あの面面に凝視されると、大人でもドキリとするんだよね。

うわさのひと…?
話の真偽は分からないが、
この怪しげな行事の起源に関し、こんな伝説がある。
源頼朝が隠れ里~佐助ガ谷~を訪れたときのこと。
ある木彫師の娘に魅せられ、
お忍びで何度となくこの娘のもとに通う。
その後、その娘を妊娠させたことを
正妻である政子に知られるのを恐れた頼朝は、
この父娘に藍摺の布ニ反を与え、
この地域の一族に一年に一度だけの無礼講を許した。
この行列は、その様子を再現したものという。
十人集のうち九番目の「阿亀」の面が、
頼朝が孕ませたといわれる娘で、
今でも大きなお腹で参加することが習わしとなっている。
口封じに藍摺ニ反?、無礼講と行列??
むむむ…何とも不可思議な日本むかしばなし。
この怪しげな行事の起源に関し、こんな伝説がある。
源頼朝が隠れ里~佐助ガ谷~を訪れたときのこと。
ある木彫師の娘に魅せられ、
お忍びで何度となくこの娘のもとに通う。
その後、その娘を妊娠させたことを
正妻である政子に知られるのを恐れた頼朝は、
この父娘に藍摺の布ニ反を与え、
この地域の一族に一年に一度だけの無礼講を許した。
この行列は、その様子を再現したものという。
十人集のうち九番目の「阿亀」の面が、
頼朝が孕ませたといわれる娘で、
今でも大きなお腹で参加することが習わしとなっている。
口封じに藍摺ニ反?、無礼講と行列??
むむむ…何とも不可思議な日本むかしばなし。