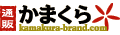鎌倉好き集まれ!JUNEさんの鎌倉リポート・第26号(2004年10月17日)
On the autumn breeze
滑川上流の十二所に、時宗の寺 光触寺がある。
本堂前の地蔵堂には、石造りの六地蔵が祀られている。
ややずんぐりとした風貌は、庶民の地蔵信仰の深さを物語る。
かつては商人が行交う賑やかな金沢街道に面して建てられていた。
その昔、六浦から朝比奈峠を越え鎌倉へ向かう塩売りが、
この地蔵尊に初穂の塩を供えていくと、
帰りにはその塩が跡形もなく消えていたことから、
「塩嘗地蔵」と呼ばれるようになった。
当時の金沢街道が、重要な「塩の道」であったことを偲ばせる。
くれぐれも、塩分は控えめに・・・ね。
本堂前の地蔵堂には、石造りの六地蔵が祀られている。
ややずんぐりとした風貌は、庶民の地蔵信仰の深さを物語る。
かつては商人が行交う賑やかな金沢街道に面して建てられていた。
その昔、六浦から朝比奈峠を越え鎌倉へ向かう塩売りが、
この地蔵尊に初穂の塩を供えていくと、
帰りにはその塩が跡形もなく消えていたことから、
「塩嘗地蔵」と呼ばれるようになった。
当時の金沢街道が、重要な「塩の道」であったことを偲ばせる。
くれぐれも、塩分は控えめに・・・ね。

塩嘗地蔵
僅かに開いた本堂障子の隙間から中を覗く。
秋晴れの眩しい陽光に慣れた目では、
この暗闇の内部まではやはり見えない。
期待していた頬焼阿弥陀仏との初対面を諦めて、
本堂奥の庭園へ。
愛らしい花名とその繊細な花形についうっとり。
「ホトトギス」という和名の由緒は、
白地に紫色の斑点が散在するこの花模様が、
鳥のホトトギスのお腹の斑紋に似ているため。
「時鳥」「霍公鳥」「不如帰」「杜鵑草」…
漢字遊びもここまでくると…少し疲れるかな。
秋晴れの眩しい陽光に慣れた目では、
この暗闇の内部まではやはり見えない。
期待していた頬焼阿弥陀仏との初対面を諦めて、
本堂奥の庭園へ。
愛らしい花名とその繊細な花形についうっとり。
「ホトトギス」という和名の由緒は、
白地に紫色の斑点が散在するこの花模様が、
鳥のホトトギスのお腹の斑紋に似ているため。
「時鳥」「霍公鳥」「不如帰」「杜鵑草」…
漢字遊びもここまでくると…少し疲れるかな。

ホトトギス

秋影
当時、十二所は政所から鬼門の方位にあった。
鎌倉の安泰を願った幕府は、明王院を鬼門除け祈願寺として
《不動》《降三世》《軍荼利》《大威徳》《金剛夜叉》の
五大明王を祀った。
それぞれの明王に大きなお堂があったことから
「五大堂」とも呼ばれる。
「只今戻りました」
背後で威勢のいい声がし、くるりと振り向くと、
寺の玄関先に、白い法衣を着た若い僧侶が立っている。
未だ青き坊主頭と足元の真っ白な足袋が溌剌として眩しい。
がんばれ~、未来の住職さん!
鎌倉の安泰を願った幕府は、明王院を鬼門除け祈願寺として
《不動》《降三世》《軍荼利》《大威徳》《金剛夜叉》の
五大明王を祀った。
それぞれの明王に大きなお堂があったことから
「五大堂」とも呼ばれる。
「只今戻りました」
背後で威勢のいい声がし、くるりと振り向くと、
寺の玄関先に、白い法衣を着た若い僧侶が立っている。
未だ青き坊主頭と足元の真っ白な足袋が溌剌として眩しい。
がんばれ~、未来の住職さん!

曼殊沙華
カサカサと枯葉舞う参道。
冠木門をくぐると、茅葺屋根の本堂が現れる。
境内はすっかり秋模様。
爽涼の空に、天高くたわわに実る柿の木。
苔生す灯篭に寄り添い、赤い曼殊沙華が風にそよぐ。
その群の中に、紅ならぬ白一点、神秘の空間を発見。
幻想的かつ妖艶な風情の白い曼殊沙華。
まるであの世の川岸に咲いているかの如くひっそりと、
只々独り静かに。
冠木門をくぐると、茅葺屋根の本堂が現れる。
境内はすっかり秋模様。
爽涼の空に、天高くたわわに実る柿の木。
苔生す灯篭に寄り添い、赤い曼殊沙華が風にそよぐ。
その群の中に、紅ならぬ白一点、神秘の空間を発見。
幻想的かつ妖艶な風情の白い曼殊沙華。
まるであの世の川岸に咲いているかの如くひっそりと、
只々独り静かに。
明王院から裏山へと続くハイキングコースの入口に
うっそうと繁る竹林。
数年前に、友人と二人でこの山道を歩いたときのこと。
「竹の花って知ってる?」
「ごく稀に、稲穂状の黄緑花をつけるんだって」
「それがとっても清楚で素朴な花らしいの」
「でもね、開花したら最後、
惜しくもその竹は枯死してしまうんだって」
すると、笹の繁みから一羽の黒い烏がバサッと飛び立った。
静寂を破る突然の物音に、ブルルと身震い。
続いて背筋がゾクゾク・・・何となく寒気が。
生命の終焉って…なんだろうなぁ。
うっそうと繁る竹林。
数年前に、友人と二人でこの山道を歩いたときのこと。
「竹の花って知ってる?」
「ごく稀に、稲穂状の黄緑花をつけるんだって」
「それがとっても清楚で素朴な花らしいの」
「でもね、開花したら最後、
惜しくもその竹は枯死してしまうんだって」
すると、笹の繁みから一羽の黒い烏がバサッと飛び立った。
静寂を破る突然の物音に、ブルルと身震い。
続いて背筋がゾクゾク・・・何となく寒気が。
生命の終焉って…なんだろうなぁ。

竹林