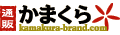鎌倉好き集まれ!わびすけ☆さんの鎌倉リポート・第559号(2009年9月18日)
☆”鎌倉神楽”を楽しく鑑賞、長谷/御霊神社!
◆大例祭で、鎌倉神楽が行われた、御霊神社!

◇③「笹の舞(ささのまい)」
鎌倉坂ノ下にある御霊神社の例大祭で、鎌倉市の無形文化財にも指定されている”鎌倉神楽”が執り行われました。
鎌倉時代から伝わる湯立をともなう神楽で、神楽座の脇の大釜で湯が立てられ、祓と吉凶を占う神事だそうです。
宮司さんの解説に従って古神楽が執り行われました。
①「御幣招(ごへいまねき)」:御幣を捧げて四方拝の舞を行い、神々を招き寄せる
②「掻湯(かきゆ)」:御幣の柄で大釜の湯を掻き回し 釜の中央から湯花を立てて吉凶を占う
③「笹の舞(ささのまい)」:神官二人の笹舞の後、湯に笹を浸して振り回し祓いを行う
④「射祓(いはらい)」:四方にいる悪しき者を竹の矢で射祓う
⑤「剣舞もどき(けんまいもどき)」。天狗と山ノ神が二人で舞う
「剣舞もどき」は、天下泰平・家内安全を願う天狗の舞を、山ノ神が道化役となって邪魔するコミカルな舞。
参拝者が神事で緊張した状態から、再び日常へと戻っていくというい意味から「もどき」と言われるそうです。
観衆のみんなが楽しみ、笑顔で幸せを持ち帰る神事なんですね。
鎌倉時代から伝わる湯立をともなう神楽で、神楽座の脇の大釜で湯が立てられ、祓と吉凶を占う神事だそうです。
宮司さんの解説に従って古神楽が執り行われました。
①「御幣招(ごへいまねき)」:御幣を捧げて四方拝の舞を行い、神々を招き寄せる
②「掻湯(かきゆ)」:御幣の柄で大釜の湯を掻き回し 釜の中央から湯花を立てて吉凶を占う
③「笹の舞(ささのまい)」:神官二人の笹舞の後、湯に笹を浸して振り回し祓いを行う
④「射祓(いはらい)」:四方にいる悪しき者を竹の矢で射祓う
⑤「剣舞もどき(けんまいもどき)」。天狗と山ノ神が二人で舞う
「剣舞もどき」は、天下泰平・家内安全を願う天狗の舞を、山ノ神が道化役となって邪魔するコミカルな舞。
参拝者が神事で緊張した状態から、再び日常へと戻っていくというい意味から「もどき」と言われるそうです。
観衆のみんなが楽しみ、笑顔で幸せを持ち帰る神事なんですね。

◇大例祭の幟と江ノ電、御霊神社!

◇④「射祓(いはらい)」悪を矢で射る!

◇⑤「剣舞もどき」天狗の舞!

◇②「掻湯」大釜の湯立て!

◇③「笹の舞」釜の湯に笹を浸ける!

◇③「笹の舞」湯のついた笹を振り回す!

◇③「笹の舞」湯に当たればお祓いになる!
◆鎌倉神楽の後、面掛行列が始まりました!

◇歴史を感じる神輿の鳳凰!
御霊神社の境内で鎌倉神楽が演じられた後、前号で紹介した”面掛行列”がスタートしました。
行列を見た後、由比ヶ浜に出ると海の家はすっかり撤収中。波打ち際に積み重なった柱の風景を観ると、夏の終わりを実感しますね。
~おしまい~
行列を見た後、由比ヶ浜に出ると海の家はすっかり撤収中。波打ち際に積み重なった柱の風景を観ると、夏の終わりを実感しますね。
~おしまい~

◇夏のおわり、海の家も撤収!