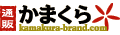鎌倉好き集まれ!与太郎さんの鎌倉リポート・第2号(2004年8月1日)
満福寺 笛供養

腰越にある満福寺は、744年(天平16年)に開かれた、頼朝が鎌倉に入るずっと前からある古いお寺です。

このお寺は、源義経が滞在し、腰越状を書いた所として有名です。
境内には、弁慶の手毬石や腰掛石などがあります。
境内には、弁慶の手毬石や腰掛石などがあります。

本堂内には、鎌倉彫の技法を活かした義経の生涯を物語る襖絵が32面あります。
義経がここで腰越状を書いたのは、1185年(元暦2年)6月5日とのことと云われています。
義経がここで腰越状を書いたのは、1185年(元暦2年)6月5日とのことと云われています。

義経は笛の名手でもあったそうです。
その義経を偲んでの笛供養が、腰越状が書かれた頃にあわせて、毎年6月の第1土曜日に催されます。
その義経を偲んでの笛供養が、腰越状が書かれた頃にあわせて、毎年6月の第1土曜日に催されます。

この笛供養では、静の舞も披露されます。
八幡宮舞殿の静の舞とはまた趣の違うものです。
八幡宮舞殿の静の舞とはまた趣の違うものです。