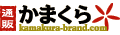鎌倉の歩き方
大町を歩く
日蓮上人ゆかりの寺を巡る
スタートは鎌倉駅東口
日蓮上人は、鎌倉時代の仏教の僧。鎌倉仏教のひとつである日蓮宗の宗祖です。鎌倉での宗教活動を理由に、北条時宗によって佐渡に流罪にされました。
大町方面にある日蓮上人ゆかりの寺を巡ってみましょう。
鎌倉駅東口からスタートです。 2分
2分
大町方面にある日蓮上人ゆかりの寺を巡ってみましょう。
鎌倉駅東口からスタートです。
 2分
2分大巧寺

日蓮上人辻説法跡

日蓮上人が小町大路で法華経の正しいことを、辻々にたち人々に説きました。これを辻説法といい、おこなった場所を日蓮上人辻説法跡と呼んでいます。その当時、鎌倉を南北に結ぶ道路であった小町大路は、武家屋敷と商家町との境になっていたところでもあり、非常に人通りが多いところでした。ここは多くあった辻説法跡の一つです。 6分
6分
 6分
6分本覚寺

日蓮上人の分骨が納められているお堂
妙本寺

総門をぬけて参道に入るとその奥一帯の谷戸が妙本寺の境内で、このあたりは比企ヶ谷と呼ばれています。もともと妙本寺は、比企一族の屋敷跡に建てられました。鎌倉幕府の重臣であった比企一族は後に北条氏に惨殺され、辛うじて生き残った日蓮の弟子となった比企三郎能本が、師である日蓮のためと比企一族の霊を弔うためにお堂を建てたのが、妙本寺の始まりとされています。
石段を登り朱塗りの二天門をくぐると、正面に祖師堂、右側に比企一族の墓、左側に開山された日朗上人像があります。いまも日蓮宗の格式の高い寺院の一つで、戦前までの住職は、東京の池上本門寺の住職が兼務するならわしになっていたといわれています。
祖師堂に日蓮上人坐像(現在は霊宝殿)が安置されており、この像は、身延山や本門寺の像とともに日蓮上人の生前の姿をうつした三体の像といわれています。 5分
5分
石段を登り朱塗りの二天門をくぐると、正面に祖師堂、右側に比企一族の墓、左側に開山された日朗上人像があります。いまも日蓮宗の格式の高い寺院の一つで、戦前までの住職は、東京の池上本門寺の住職が兼務するならわしになっていたといわれています。
祖師堂に日蓮上人坐像(現在は霊宝殿)が安置されており、この像は、身延山や本門寺の像とともに日蓮上人の生前の姿をうつした三体の像といわれています。
 5分
5分「ぼたもち寺」常栄寺

「ぼたもち寺」と呼ばれる常栄寺。日蓮上人が馬で刑場に引かれていくときに、法華宗の信者であった桟敷尼が日蓮に「仏のご加護がありますように」とぼたもちを差し上げたところ、処刑されようとした日蓮上人が奇跡的に竜の口で救われました。それから、奇跡が起こったのは「桟敷尼の差し上げたぼたもちのご利益に違いない」として、毎年9月12日の御法難会のとき、この寺から龍口寺や妙本寺の日蓮上人の像にぼたもちが供えられることになっています。 5分
5分
 5分
5分上行寺

本堂右手の薬師堂
上行寺の現在の本堂は、名越松葉ヶ谷の妙法寺の法華堂を移築したものといわれています。
本尊は三宝祖師、本堂内正面に日蓮上人像、左手に開山日範上人像が安置されています。諸病一切を治すという瘡守稲荷をまつる稲荷堂と大小の鬼子母神を祀る薬師堂が本堂右手に建っています。 8分
8分
本尊は三宝祖師、本堂内正面に日蓮上人像、左手に開山日範上人像が安置されています。諸病一切を治すという瘡守稲荷をまつる稲荷堂と大小の鬼子母神を祀る薬師堂が本堂右手に建っています。
 8分
8分苔寺・妙法寺


妙法寺のあたりから安国論寺・長勝寺にかけての地域は名越・松葉ヶ谷と呼ばれ、日蓮が鎌倉での法華経を広める足場とした草庵があったところです。またこの地域は、日蓮に反感をもっていた鎌倉の武士や僧たちによって、1260年(文応元年)に焼き打ちされました。これを松葉ヶ谷法難といっています。
護良親王(もりながしんのう)の遺子日叡が父の霊を弔うために寺を再興したのが妙法寺の始まりとされています。本堂右奥の仁王門をくぐると正面に苔の石段があり「鎌倉の苔寺」ともいわれています。 3分
3分
護良親王(もりながしんのう)の遺子日叡が父の霊を弔うために寺を再興したのが妙法寺の始まりとされています。本堂右奥の仁王門をくぐると正面に苔の石段があり「鎌倉の苔寺」ともいわれています。
 3分
3分